2022.04.22
ゼロエミッションとは?東京戦略や企業の取り組み事例を紹介 0

目次
地球温暖化の問題が数十年前から指摘されてきたなか、いま注目を集めている概念の1つに「ゼロエミッション」があります。近年ではゼロエミッションを目標として掲げる企業や自治体も増えてきました。
今回の記事では、ゼロエミッションの概念や関連の深い「3R」について詳しく解説するとともに、国や自治体、企業における取り組み事例も紹介します。
ゼロエミッションとは

はじめにゼロエミッションについて、言葉の意味や概要、注目されている背景を解説します。
廃棄物を自然界に排出しない取り組み
ゼロエミッションとは、人間の活動から生まれる排出物を限りなくゼロに近づけることを目指して資源活用を図り、持続可能な経済・生産活動を展開する理念と手法のことです。
1994年に国際連合大学が提唱した概念で、排出(エミッション)をゼロにするという意味をもちます。
例えば工場で物を生産する場合、製造過程において様々な廃棄物や副産物が生じます。通常これらは産業廃棄物として処理されますが、別の生産拠点において”原材料”として活用すれば、自然界への廃棄物の排出をゼロに近づけることができます。
ちなみに現在は廃棄物だけでなく「CO₂実質排出ゼロ」の意味合いとしてもゼロエミッションという言葉が使われるようになっており、脱炭素化に向けたポイントの1つとなっています。「カーボンニュートラル」という言葉が、ゼロエミッションと同じ文脈で使われていることも多くあります。
【関連記事】カーボンニュートラルについてはこちらの記事で分かりやすく解説しています。
ゼロエミッションが注目されている背景
1994年に提唱されたゼロエミッションは近年になって再び注目されるようになりました。この背景には、持続可能な社会を目指す「サステナビリティ推進」への注目と社会的要請の高まりがあります。
現在、企業には事業を推進することだけでなく「地球や社会に与える影響にまで配慮すること」が強く求められるようになっています。こうした考え方と、生産活動のみに目を向けずに廃棄物の排出削減を図るゼロエミッションの概念は、非常に親和性の高いものなのです。
【関連記事】ESG経営とは?
さらに「カーボンニュートラル」が国の目標として掲げられたこと、東京都が「ゼロエミッション東京」という戦略を打ち出したことなども、ゼロエミッションが注目を浴びるきっかけとなりました。
ゼロエミッションで大切な「3R」とは

世界では産業革命以降、多くの国が急速に発展を遂げてきました。しかし、その過程において「大量資源採取」・「大量生産」・「大量消費」・「大量廃棄」が繰り返されてきたことも事実であり、これらによって経済が支えられてきたといっても過言ではありません。
こうした状況から脱却してゼロエミッションを実現するにあたり、大切になるのが「Reduce・Reuse・Recycle」を総称した「3R」とよばれる概念です。
1.「Reduce(リデュース)」廃棄物の発生抑制
「Reduce」とは、廃棄物の排出量を減らすことを意味します。
原材料を無駄なく使い切ることや製品の軽量化・軽包装化を進めること、また、耐久性に優れた長く使える製品を提供することなどが「Reduce」にあたります。「排出量削減」の意味合いでは、工場で使用する電力を”再生可能エネルギー”へ切り替えて二酸化炭素の排出量を削減する方法などが考えられるでしょう。
廃棄物の排出を極限まで減らすことは環境対策の基本であり、再使用や再生利用にかかるコストを削減することにもつながります。
【関連記事】日本の再生可能エネルギーが高いといわれる理由について、分かりやすく解説しています。
2.「Reuse(リサイクル)」再使用
「Reuse」とは、使用していた製品や部品を廃棄することなく繰り返し使用することを意味します。
生産拠点の移転や縮小などのタイミングで不要になった機器を、廃棄処分せずに別の拠点で再使用すること、また他社に買い取ってもらうことなどが「Reuse」にあたります。
3.「Recycle(リサイクル)」再生利用
「Recycle」とは、本来廃棄物として処理するものを別の形に再生し利用することを意味します。
缶や瓶などの資源ごみを回収して再加工するといった例のほかに、生ごみをバイオマス発電のエネルギー源とする方法や、ごみ焼却施設からの熱源を温水プールなどに活用する方法も「Recycle」にあたります。
一見すると廃棄するほかに手段がないと思えるようなものでも、工夫次第では様々な再生利用の方法が存在し、「Reuse」とあわせることで廃棄物の発生を限りなくゼロに近づけることができます。
【関連記事】バイオマス発電の基礎について分かりやすく解説しています。
ゼロエミッションの実現に向けた動き

ゼロエミッションの実現に向けて、日本では具体的にどのような動きが生まれているのでしょうか。本章では国や自治体の取り組みをご紹介します。
2050年カーボンニュートラル宣言
2020年10月に菅内閣総理大臣は、所信表明演説のなかで「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」ことを宣言しました。そしてこれをクリアするための中期的な目標として、「2030年度までに2013年度比で温室効果ガス46%を削減する」を表明しています。
この宣言が出されたことは、「CO₂実質排出ゼロ」の意味合いでのカーボンニュートラル実現を目指す取り組みを加速させる契機になりました。
温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることは「脱炭素」や「カーボンニュートラル」ともよばれ、温室効果ガスの排出量と吸収量・除去量の差分をゼロにすることを意味します。森林が吸収できる温室効果ガスの量は限られているため、排出量そのものを削減することはもちろん、再生利用によってトータルでの排出量を削減していくことも重要です。
<!–
企業が求められているカーボンニュートラルの取り組みについて、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
–>
東京都の「ゼロエミッション東京戦略」
「ゼロエミッション東京戦略」とは、2030年までに温室効果ガスの排出量を50%削減する「カーボンハーフ」を実現するため、東京都が具体的な戦略として策定したものです。このなかで、重点的対策が必要な3つの分野と方針を以下のように示しました。
- 気候変動を食い止める「緩和策」と、既に起こり始めている影響に備える「適応策」を総合的に展開
- 資源循環分野を本格的に気候変動対策に位置付け、都外のCO₂削減にも貢献
- 省エネ・再エネの拡大策に加え、プラスチックなどの資源循環分野や自動車環境対策など、あらゆる分野の取組を強化
2030年に到達すべき主要目標としては「17の項目」を定め、さらに具体的な取り組みとして47項目・82のアクションから構成される「2030年目標+アクション」を設定しています。
「ゼロエミッションフォーラム」の設立
ゼロエミッションの実現に向けた取り組みには専門的な技術や設備が必要になることから、各企業が個別で取り組むだけでなく、分野や業種の垣根を超えた企業間の連携、そして産官学の連携が不可欠です。 そこで、国連大学協力会のもと、2000年に「ゼロエミッションフォーラム」が設立されました。
ゼロエミッションフォーラムでは、産業界と学会、中央官庁と連携した共同研究や情報交換など、様々な活動をおこなっています。
企業のゼロエミッションを目指す取り組み事例

ゼロエミッションを実現するために、国や自治体では「ゼロエミ・チャレンジ」や東京都によるベンチャー・中小企業への補助金など、多様な形で企業の取り組みを支援してきました。
ゼロエミ・チャレンジ企業には2021年10月時点で623社がリストアップされるなど、多くの企業が取り組みを推進しています。ここからは、代表的な企業の取り組み事例を業種別にご紹介します。
【製造業】中古バッテリーの再資源化
製造業では、「循環型リサイクル」を実現するための取り組みとして、自動車をはじめとする様々な用途に欠かせないバッテリーを、細かく粉砕してから分別し、純度の高い原料として抽出しています。
また、使用済みのバッテリーを分解して性能を評価したうえで、それぞれの用途に合わせた”再利用”も実施されています。
【卸売業】国内事業所の使用電力100%実質CO₂フリー化
国内には、本社ビルおよび事業所で使用する電力を再生可能エネルギー由来のものに転換し、「実質CO₂フリー化」を実現した商社があります。
【卸売業】アンモニア・水素を活用したゼロエミッション火力の開発
火力発電に用いられる石油や天然ガスを焼却すると二酸化炭素が排出されてしまいますが、ここに「アンモニア」や「水素」を混ぜ合わせCO₂排出量を削減する、「ゼロエミッション火力」の開発が進められています。
現在は、一部の非効率な火力発電所において石炭火力の利用を廃止するとともに、高効率な発電所ではアンモニアの混焼実験を推進しながら、アンモニア・水素による「ゼロエミッション火力」の実用化が目指されています。
【関連記事】アンモニアがどのようにサステナブルな世界を作るのか、アンモニアの燃料としての可能性などを下記の記事で解説しています。
【運輸・郵便業】CO₂排出量100%削減のコンセプトシップ考案
貨物船の燃料として活用されてきた化石燃料の代わりに水素を利用し、船上には太陽光パネルを搭載した「コンセプトシップ」は、CO₂の排出量の100%削減を実現しました。船体の軽量化と形状の見直しによって摩擦抵抗を極限まで減らし、従来の貨物船にくらべて70%ものエネルギーを削減しています。
【建設業】廃棄物予測とメーカーリサイクルの活用
大手建設メーカーでは独自に開発したシステムによって、建物から排出される廃棄物の量を予測し、設計の段階で使用材料や工法の検討をおこなっています。廃棄物の最終処分量のシミュレーションや、結果をもとに廃棄物量を削減する取り組みもおこなわれています。
また、メーカーごとに建設廃棄物の回収を徹底し、製造からリサイクルまでを同一メーカーで担うことで、資源の循環効率を最大化することにも成功しました。
【情報通信業】再エネ主力電源化への貢献
再生可能エネルギーの発電設備や蓄電池といった分散化している電源を統合し、リモートから制御することにより、仮想的に大規模発電所のように稼働できるシステムが開発されました。この取り組みは再生可能エネルギーの電力系統の安定化を支え、主力電源化を後押しするものと期待されています。
【地方自治体】地方の特徴を活かした取り組みを模索
地方自治体では、地方の特徴を活かした以下のような検討が既に開始されています。
- 水を使わずに、木質バイオマスを利用したORC(オーガニック・ランキン・サイクル)システム(ヨーロッパでは既に200基くらいの導入実績あり)
- 食品残渣・藻類等の資料化、IT活用による養殖等の省力化 など
まとめ

ゼロエミッションとは「人間の活動から生まれる排出物を限りなくゼロに近づけることを目指して資源活用を図り、持続可能な経済・生産活動を展開する理念と手法」のことを指します。1990年代に登場した概念で、サステナビリティ推進が注目されるようになった現在、再び脚光を浴びるようになりました。
ゼロエミッションの実現は、国や自治体、企業単位だけの課題にはとどまりません。サプライチェーンがグローバル化している現在においては、地球全体の課題として捉え、それぞれが連携しながら活動を進めることが求められているのです。


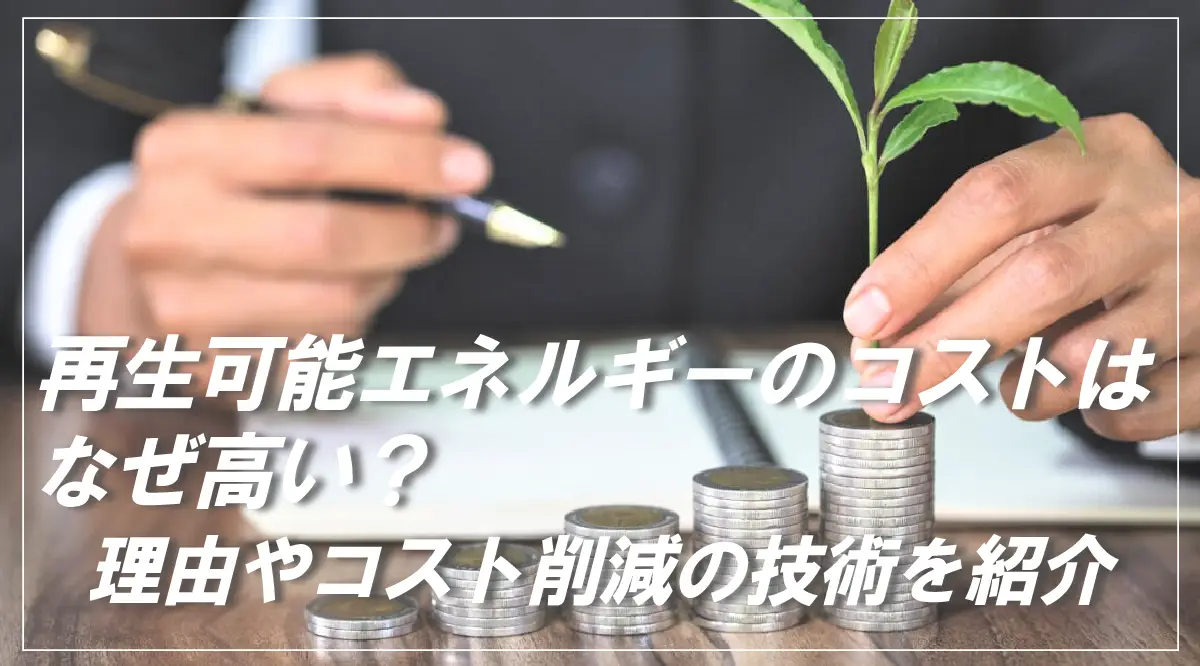


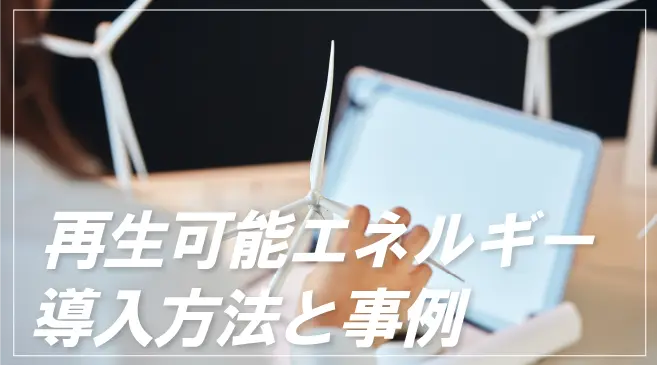

COMMENT
現在コメントはございません。