2022.04.22
企業に求められるサステナビリティとは?意味や取り組みまで解説 0

目次
「サステナビリティ」という言葉は、近年さまざまなシチュエーションで耳にする機会が増えた言葉のひとつではないでしょうか。そして企業においても、「サステナビリティ」に取り組むことが求められている社会になってきました。
そこで今回は、改めてサステナビリティの意味を解説するとともに、サステナビリティにまつわる現状や課題、企業が取り組むべき理由を事例と合わせて紹介します。
サステナビリティとは

環境・社会・経済が持続的に発展する社会の実現を目指す考え方のこと
サステナビリティ(持続可能性)とは、英語の「sustain(支える、持続させる)」と「-bility(可能性)」を組み合わせた言葉で、「環境・社会・経済が持続的に発展する社会の実現を目指す考え方」をさします。
現代では環境問題や貧困などの社会問題が深刻化していることから、「地球環境と人類を守るためには、短期的な行動ではなく中長期的な視点で発展することが必要不可欠だ」という認識が世界共通となっています。
こうした背景のもと「サステナビリティ」の言葉は広がりを見せ、世界各国で持続可能な社会の実現に向けた動きが拡大しています。
サステナビリティの3つの柱
サステナビリティが注目されたきっかけのひとつには、2005年におこなわれた世界社会開発サミットがあります。本サミットでは、「経済開発(Economic Development)」・「社会開発(Social Development)」・「環境保護(Environmental Protection)」の3方針が採択されました。
持続可能な社会の実現には「経済活動」の推進だけでなく、経済活動で生じる「環境」や「社会」への影響も踏まえた行動が必要とされています。
サステナビリティとSDGs、CSRとの違い
サステナビリティと混同されやすい「SDGs」や「CSR」について、違いを説明できる方は少ないのではないでしょうか。ここからは、サステナビリティと混同されがちな用語についてその違いを解説します。
SDGsとの違い
SDGsは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の頭文字を取ったもので、持続可能な世界を実現するための国際目標です。対象はすべての国と人々で、「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを原則としています。つまりサステナビリティは持続可能な社会の実現を目指す考え方であるのに対し、SDGsは2030年を達成期限とする目標であるといえるでしょう。
【関連記事】サステナビリティとSDGsの違いについては、こちらの記事で解説しています。
CSRとの違い
CSRは「Corporate Social Responsibility(⇒企業の社会的責任)」の頭文字をとった言葉で、企業が果たすべき社会的責任のことです。
企業は規模が大きくなると、それに比例して従業員などの「ステークホルダー」が増え、社会に与える影響も同じように増大します。「CSR」は、これらの社会的な責任を「社会貢献活動で埋め合わせる」という企業側の意味合いが強い言葉です。
【内容別】企業のサステナビリティへの取り組み事例

各業界・業種ではサステナビリティの実現に向けた取り組みが広がっています。本章ではサステナビリティの柱となる「環境・社会・経済」の3つの観点から、企業のサステナビリティ取り組み事例を紹介します。
環境への取り組み:帝人フロンティア・P&G・カプコン
|
帝人フロンティア
|
海洋環境への影響が懸念されるマイクロプラスチックの排出削減に向け、洗濯によって生じる繊維くずの発生を抑制した新素材を開発 |
|
P&G
|
「気候変動・廃棄物・水・自然」の4つの柱を立て、サステナビリティへの取り組みを実施 |
|
カプコン
|
コンテンツのデジタル販売推進や、設備の入れ替えなどによる環境負荷の低減、またCO2排出量削減などへの取り組みを実施 |
(参照:帝人フロンティア「海洋環境への影響が懸念されるマイクロプラスチックの排出削減の取組事例」,P&G「環境サステナビリティ」,カプコン「環境への取り組み」)
社会への取り組み:日本航空・ジモティー・マザーハウス
|
日本航空
|
「TABLE FOR TWO 社員食堂プログラム」やユニセフ支援などを通じ、世界の貧困対策への取り組みを実施 |
|
ジモティー
|
ひとり親世帯に向けた支援物資の受け渡し会を継続的に開催 |
|
マザーハウス
|
バングラデシュの直営工場における持続可能な労働環境の整備などを実施 |
(参照:日本航空「社会貢献活動」,ジモティー「SDGsに関する取り組みについて」,マザーハウス「ABOUT US」)
経済への取り組み:UCC上島珈琲・生活協同組合ユーコープ・日本郵政
|
UCC上島珈琲
|
2030年までに、自社ブランドで100%サステナブルなコーヒー調達に向けた取り組みを実施中 |
|
生活協同組合コープ
|
環境負荷の低減と持続可能な畜産業や酪農業を目指し、コープの産地指定「はぐくみ鶏」で循環型農業を形成 |
|
日本郵政
|
「人と共に」のスローガンのもと、一人ひとりが能力を発揮できる環境づくりを進め、持続可能な経済成長を目指し中 |
(参照:UCC上島珈琲「100%サステナブルなコーヒー調達に」,生活協同組合ユーコープ「環境を守る:循環型の農畜産業や酪農」,日本郵政「サステナビリティ:人と共に」)
【3選】企業がサステナビリティへ取り組むべき理由

さまざまな理由から、自社でサステナビリティを推進するのは難しいと感じる場合もあるかもしれません。しかし、取り組むことで得られる利点もあり、本章では企業がサステナビリティに取り組むべき理由を紹介します。
事業規模・範囲の拡大が見込める
企業がサステナビリティに取り組む理由の1つに、事業規模や事業範囲の拡大が見込めることが挙げられます。
たとえば、既存のビジネスモデルをサステナビリティにあわせて転換・アップデートをしたり、あらたに新規事業を実行することもサステナビリティへの取り組みです。こうしたアクションがきっかけとなり、事業の成長につながるケースは少なくありません。
ブランドイメージが向上する
サステナビリティに積極的に取り組んでいる企業は、企業イメージが向上する可能性もあります。
国内・国外共に、ビジネスにおけるサステナビリティへの関心は日々高まっており、率先して持続可能性を模索する姿は多くのステークホルダーの目に留まるといえます。さらに昨今は、「ESG投資」という言葉が注目を浴びているのをご存知でしょうか。ESG投資は、環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)の3つの要素を考慮しておこなう投資のことです。
【関連記事】ESG投資の基礎やメリット・デメリットはこちらの記事で解説しています。
サステナビリティな取り組みに力を入れる企業は投資家からの信用が大きくなり、企業ブランドのイメージ向上や企業価値の高まりにもつながるかもしれません。さらに最近ではサステナビリティへの取り組みを評価する消費者や、持続可能性を基準として商品を選ぶような消費者も増加傾向にあるため、売上の増加にもつながります。
【関連記事】「環境(Environment)」「社会(Social)」「企業統治(Governance)」の3つの要素を重視した経営を指す「ESG経営」の基礎については、こちらの記事で解説しています。
従業員のエンゲージメントが向上する
サステナビリティへの取り組みには、働く環境の改善も含まれます。労働環境が向上され、快適になることで従業員のエンゲージメントは高まり、企業理念の定着や企業に対する愛着、所属感の強化も見込めるかもしれません。このような理由から、近年はサステナビリティに取組む企業が増加傾向にあります。
【関連記事】企業における「サステナビリティ委員会」の役割や設立の流れについては、こちらの記事で解説しています。
サステナビリティにはこんな課題も

一方でサステナビリティの取り組みには、課題も存在します。ここからは、日本におけるサステナビリティの課題は解説します。
2023年版世界のSDGsランキングで日本は21位
持続可能な開発ソリューション・ネットワークとベルステルマン財団によって発行された、「Sustainable Development Report2023」では、「SDGsで掲げる17目標をどれだけ達成できているか」という視点で、国連加盟国の193カ国がランク付けされています。
本レポート内で日本は193ヵ国中21位に位置づけられており(※2021年レポートでは165カ国の中で18位)、アジア諸国の中では1位ですが、欧州諸国に比べると低い順位に留まっています。欧州と比較した際のサステナビリティへの取り組みの遅延や、課題解決の法整備・行政主導が行き渡っていないことが要因の1つと考えられるでしょう。
たとえば 日本において、「相対的貧困」や「女性国会議員の人数」、「男女の賃金差」などは達成がされていない目標です。SDGsの達成期限である2030年までに着手すべき問題はこれら以外にも残っており、官民連携での早急な問題解決が求められます。
サステナビリティは環境問題だけではない
「サステナビリティ」は環境問題だけに焦点を当てたものではなく、ダイバーシティ(多様性)やインクルージョン(多様性が活かされていること)の問題も包括して、持続可能な社会にしていくための概念です。地球環境を良くするという意味にとどまらず、誰もが取り残されないための「平等」や「多様性」といった面を含んだ包括的なサステナビリティへの取り組みを考えてみるとよいでしょう。
例えば、子育て世帯の負担を軽減するための福利厚生や、労働環境を整備する取り組みもサステナビリティの一環といえます。
【段階別】サステナビリティへの取り組みの始め方

ステップ1.サステナビリティへの理解を深める
最初のステップとして、サステナビリティへの理解を深めることが重要です。
サステナビリティに正しく取り組むうえで、まず知っておきたいのは以下の3つの留意点です。
- 取り組みが、企業の規模や能力に見合っていること
- 取り組みの成果が明確で、途中経過や結果を一貫した指標で報告できること
- 単発的ではなく持続可能な取り組みであること
加えて、その取り組みに「自社ならでは」の必然性があると、より望ましいかもしれません。しかしサステナビリティの課題は複雑に関連しているため、「貧困撲滅のための開発」が自然環境にはマイナスの影響を与えるなどのように、予期せぬトレードオフが生じるケースもあります。 こうした観点が抜け落ちると形だけの取り組みになってしまったり、「SDGsウォッシュ*」だと批判される可能性も出てきます。そうならないためにも、サステナビリティについての本質的な理解を深め、いろいろな立場・角度から複数の社会課題を俯瞰し、対応していくことが大切です。このような姿勢で臨めば、自社にも社会・環境・経済にも良い影響をもたらすことができるはずです。
*SDGsへの取り組みをおこなっているように見えて、その実態が伴っていないビジネスを揶揄する言葉
ステップ2.目的・目標を設定する
次のステップは、サステナビリティに取り組む目的や、サステナビリティへの取り組みによって実現したい中長期的な目標を設定することです。目標設定の方法や内容は企業によってさまざまであるため、事例を挙げてご紹介します。
ライオングループは、同社が定める「サステナビリティ重要課題」に対し、各課題の解決に向けた活動目標を設定しています。サステナビリティ重要課題の特定に当たっては【1.社会課題の抽出】【2.社会・事業への影響度を確認】【3.重要課題の妥当性を検討】【4.執行役員会・取締役会にて確認】という4つのステップを踏んでいます。
(参照:ライオン「サステナビリティ重要課題と2030年目標」)
キユーピーは、「健康寿命延伸への貢献」「資源の有効活用と持続可能な調達」「CO2排出削減」「子どもの心と体の健康支援」「ダイバーシティの推進」の5つのテーマでサステナビリティ目標を定め、目標達成への取り組みを通してグループの長期ビジョンの実現を図っています。
(参照:キユーピー「サステナビリティ目標を設定しました」)
ステップ3.取り組みに向けたロードマップを検討する
3つめのステップは、ステップ2で定めた目的・目標を実現するためのロードマップの策定です。
先ほど紹介したライオングループやキユーピーは、2030年までに達成するサステナビリティ目標に対して、達成指標として具体的な数値を定めることで、目標達成の定量的な評価をおこなっています。
企業でサステナビリティを推進するにあたっては、こちらの記事をご覧ください。
まとめ

企業でサステナビリティを推進するには、まずサステナビリティの本質を把握することが大切です。サステナビリティは環境問題だけに焦点を当てたものではなく、ダイバーシティやインクルージョンの問題も包括して、持続可能な社会にしていくための概念であることはおさえておきたいポイントです。
企業がサステナビリティに取り組むことは今や不可欠となりました。企業として持続的に成長していくためにも、サステナビリティの実現を企業の重要課題として取り入れることが必要なのです。

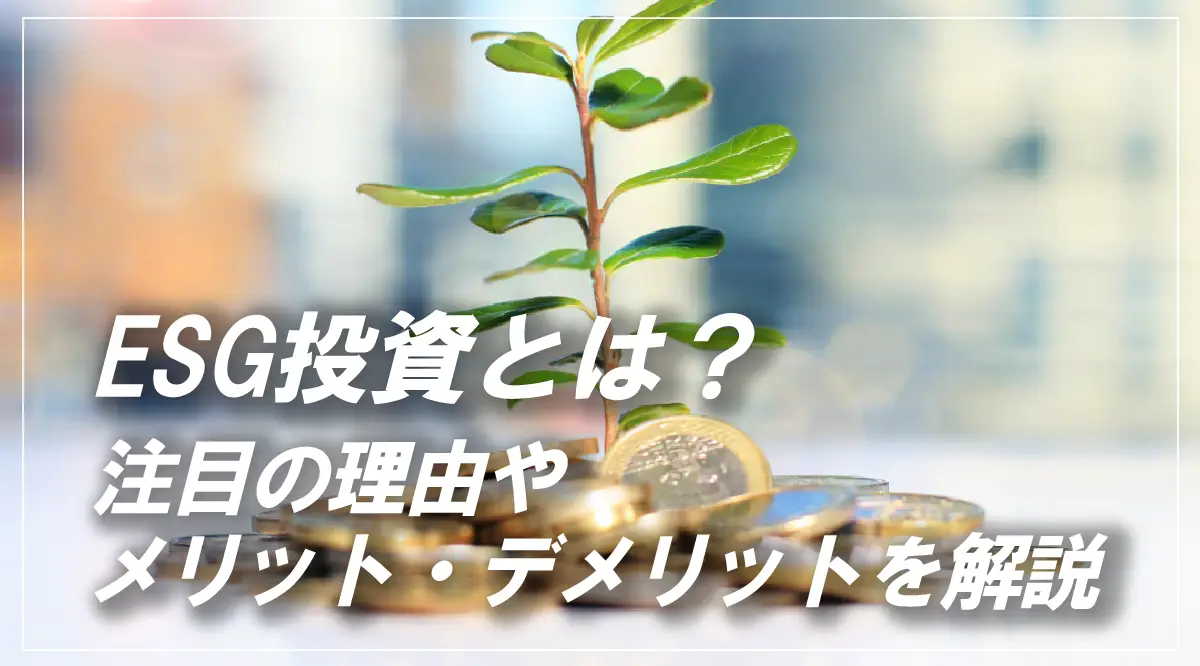

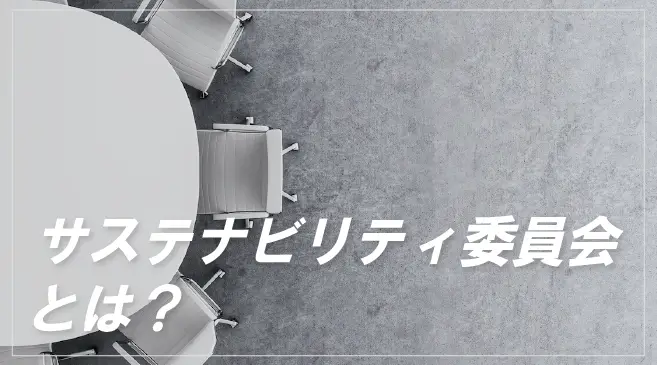
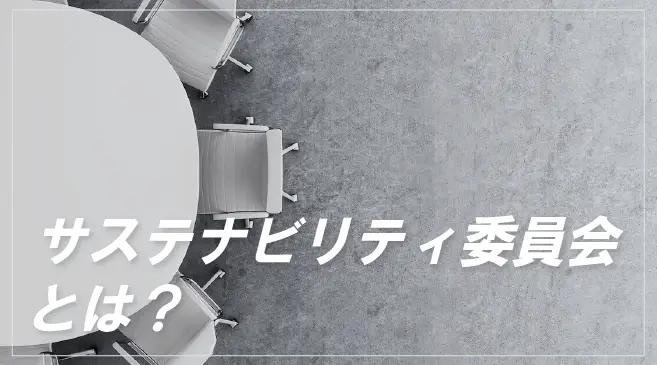

COMMENT
現在コメントはございません。