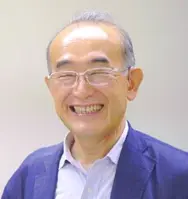2022.12.06
東大・平尾教授とひも解く繊維リサイクルの今~最終回・繊維リサイクルの現状と課題~
目次
東京大学の平尾教授へのインタビュー最終回である今回は、サステナビリティハブを運営する日揮ホールディングスも参画し共同研究を進めている「衣服のリサイクル」をメインテーマにお届けします。
衣服のいち消費者として、またはステークホルダーとして、「持続可能な循環システムを作るためにはどのような行動が必要なのか」をお伺いしました。
>>第1回・第2回・第3回はこちらから |

| 平尾 雅彦:東京大学 先端科学技術研究センター 教授 工学博士 (写真右) |
| ライフサイクルアセスメントを通じて、消費と生産パターンの変革を目指した研究をおこなっている。製造・輸送・回収・リサイクルの技術から、生産者や消費者への情報提供、社会制度の設計などのフレームワークづくりも。 サイクリングと、愛犬(長野県天然記念物の川上犬)との散歩が趣味。学生時代には、キャンピング自転車で岐阜県大垣から島根県出雲までを走破。 |
| 佐久本 太一:日揮ホールディングス株式会社 サステナビリティ協創部 (写真左) |
| 沖縄県出身。学生時代は木質バイオマス分解菌の遺伝子分析や、次世代シーケンサーを用いた菌叢解析などを研究。2019年に日本エヌ・ユー・エス株式会社に入社後、日揮ホールディングス株式会社 サステナビリティ協創部に出向し、廃繊維・廃プラスチックの資源循環ビジネス開発を担当。ダイビングとプロレス観戦が趣味。故郷の沖縄でも資源循環を達成し、美しい自然を守るのが夢。一緒に達成する持続可能なパートナーも募集中。 |
「リサイクルしやすい服」にまつわる課題

衣服のほとんどは「混紡素材」でできている
世の中に流通している衣類の半分以上は「混紡素材*」から出来ています。ですが、「本当に混紡でないと消費者が想定する衣服の価値は実現できないのか?」というのは、実はクエスチョンな気がしているんです。まだ研究はされていないものの、単一繊維でもつくれる衣服は多く存在するのでは?と思っています。
第2回でもお話したように、2種類以上の原料が混ざっている混紡は素材を分けることが難しく、リサイクルは容易ではありません。そのため「リサイクルのしやすさ」を優先して考えると、衣服の素材は「単一」がベストになります。地球環境への影響を減らし、同時に消費者が求める衣服の価値を実現する方法は他にあるはずです。いかにファッションにおける機能性・審美性を活かしつつ、リサイクルできる仕組みをつくっていくかが今後の課題なのではないでしょうか。
(*混紡:2種類以上の異なった素材の短繊維を混ぜ合わせて紡績された繊維、繊維商品のこと。(出典:日本化学繊維協会「化学繊維の用語集」最終アクセス 2022/11/24)
「繊維リサイクル」を成立させるためには何が重要か
アパレル業者が意識すべきこと・取り組むべきこと
衣服を売る側は、ぜひ販売と回収の「双方」に関わっていただきたいです。また、リサイクルしやすい設計の商品を販売(製造)すること・その良さをしっかりとアピールすることも重要です。
「ポリエステル単体」で作られた衣服はリサイクルをしやすく、「リサイクルポリエステル(再生ポリエステル)」で作られた衣服は地球環境に配慮されたものです。この魅力を消費者に伝えるのは、実際に商品を扱っているアパレル側の役目だと感じています。
最近では、”環境負荷に配慮する”という意味を含む「サステナブル」をコンセプトに掲げるアパレルブランドも増えてきましたが、このような風潮は非常に嬉しいですね。しかしその「訴求度合い」はまだ弱いようにも見えます。アパレル業者の方々は、「我々はこのようなポリシーに基づき、こういった配慮をしています。消費者の皆さんがこれを選んでくれると、地球にこんな良い影響ががあるんです。」というメッセージを、もっと全面的に伝えて欲しいです。
【番外編】「洋服のレンタル(シェアリング)が環境に良い」は言い過ぎ?
LCAの観点から見ると、「一概に環境に良いとは言い切れない。条件によって答えが異なる。」という少し曖昧な回答になります。
シェアリングは宅配で品物が運ばれ、宅配で品物を返しますが、その輸送ではCO2が排出されています。さらに「洗濯の回数」も考える必要があります。衣服を借りた人はそれを5回以上着るかもしれませんし、極端な話ですが気に入らずに1度も着ない人もいるかもしれませんよね。しかし衛生上シェアリングから戻ってきた服は、何度袖が通されていようと必ず洗わなくてはいけません。
洗濯にはもちろん環境負荷がかかるので、借りた人が1回も袖を通さなかった場合は、必要以上に洗濯をしていることになるんです。もちろん洗濯しない方がいいとは言いませんが、シェアリングすることによって洗濯の回数が増えているのだとしたら、環境に良くないことが起きているのかもしれません。
いろいろな視点から見ると、だんだん複雑でマニアックになってしまいますね。とはいえシェアリングが普及することで、「製品1つあたりの着用回数が増える」・「衣服の生産数の削減につながる可能性がある」・「消費者はコストを抑えながらいろいろなデザインの衣服を着ることができる」など、多くのメリットがあるのも事実です。
衣服を買ったきりで袖を通さずにただ持っているだけ、あるいは「ずっと着ていないから捨てよう」と手放すことに比べたら、シェアリングはとても良いことです。シェアリングを利用するときは、ちゃんと(回数を)着てあげることが重要なのかもしれません。
消費者やステークホルダーに求められていること

「燃えるゴミ」として焼却されている今の廃棄ルートを、可能な限り「リサイクル」のルートに軌道修正することが求められているのではないでしょうか。それ以外には、「サーマルリカバリー(廃棄物をガスや油、固形燃料に変えたり、燃やした際の熱を発電や蒸気として利用する方法)」によって「燃料」にするルートもあっていいと思います。またRPF*のような形にリサイクルするルートもありますが、これも実は正規のリサイクルルートだという認識を広めることも重要です。*RPF: Refuse derived paper and plastics densified Fuel の略称であり、主に産業系廃棄物のうち、マテリアルリサイクルが困難な古紙及び廃プラスチック類を主原料とした高品位の固形燃料。(出典: 日本RPF工業会「RPF」最終アクセス 2022/11/24)
化学的なリサイクル技術も積極的に使っていきたいですね。特に我々が興味あるものとしては「ポリエステル」です。ペットボトルをリサイクルして「ポリエステル原料」に変える技術は確立しているため、この技術を繊維リサイクルにも生かす仕組みを設計していきたいと考えています。
消費者に関しては、皆さんが分別しやすいように製品設計のうちからタグの作り方を工夫したり、分別しやすくなるような技術開発が重要でしょう。技術は開発したけれども、実装されずに「形」にならないことも多い世界ではありますが、繊維リサイクルを成立させるためには消費者と再生品を受け入れてくれるステークホルダーの協力が不可欠です。
そのためにはサプライチェーンのネットワーク同士がしっかりと繋がり合って、「自分たちが何をするのが1番良いのか」を考えてほしいです。 ペットボトル業界の方々は「我々はリサイクルの最先端にいる!」とおっしゃっていますが、少し前までは飲料メーカーは「再生したペットボトルなんか売れるわけない、消費者に絶対認知されません」とも言っていたようです。 ですが今では再生ペットボトルは人気の商材となっており、つまりリサイクルにまつわる状況は刻一刻と変わっているというわけです。
この移り変わりのスピード感に、繊維業界の皆さんも早く気づいてほしいと感じています。清涼飲料水業界と同様に、「自分たちはこんなに良い循環の仕組みを作っている!」と胸を張れる社会システムになってほしいですし、消費者は何よりも大事なステークホルダーだということも忘れないで欲しいですね。そのためにも、我々は正しい情報を発信していきます。
| ※「繊維・衣服の生産から流通・消費・リサイクルまでのライフサイクルを通した循環型ファッションの実現に向けて」報告書のダウンロードすることができます。こちらからご覧ください。※過去の連載はこちらからご覧ください。第1回 第2回 第3回 |