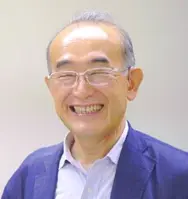2022.10.26
東大・平尾教授とひも解く繊維リサイクルの今~第1回・循環型ファッションの実現は課題だらけ?!~
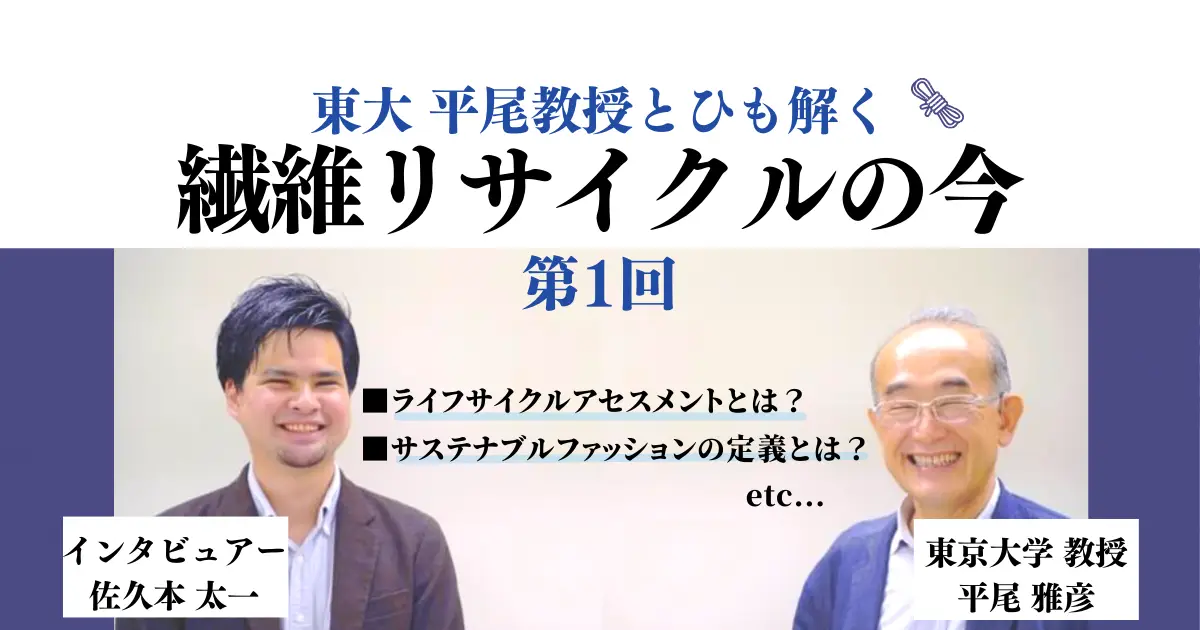
目次
私たちの誰もが毎日身に着ける衣服。ファストファッションをはじめとする安価なアイテムの普及は、「廃棄される衣服の増加理由」になっていることをご存知でしょうか。廃棄された服をゴミとせず、環境への負荷を減らすために大切なのは「リサイクル」です。
そこで今回は、日揮ホールディングスと東京大学、帝人などと共に設立したワーキンググループを率いていらっしゃる東京大学の平尾教授に、「循環型社会作りにおける衣服特有の課題」についてお話を伺いました。インタビュアーは、「衣服の循環型社会」の形成を目標にしている日揮ホールディングスの佐久本です。(連載は全4回を予定しております)

| 平尾 雅彦:東京大学 先端科学技術研究センター 教授 工学博士 (写真右) |
| ライフサイクルアセスメントを通じて、消費と生産パターンの変革を目指した研究をおこなっている。製造・輸送・回収・リサイクルの技術から、生産者や消費者への情報提供、社会制度の設計などのフレームワークづくりも。 サイクリングと、愛犬(長野県天然記念物の川上犬)との散歩が趣味。学生時代には、キャンピング自転車で岐阜県大垣から島根県出雲までを走破。 |
| 佐久本 太一:日揮ホールディングス株式会社 サステナビリティ協創部 (写真左) |
| 沖縄県出身。学生時代は木質バイオマス分解菌の遺伝子分析や、次世代シーケンサーを用いた菌叢解析などを研究。2019年に日本エヌ・ユー・エス株式会社に入社後、日揮ホールディングス株式会社 サステナビリティ協創部に出向し、廃繊維・廃プラスチックの資源循環ビジネス開発を担当。ダイビングとプロレス観戦が趣味。故郷の沖縄でも資源循環を達成し、美しい自然を守るのが夢。一緒に達成する持続可能なパートナーも募集中。 |
ライフサイクルアセスメントとは?
製品やサービスのライフサイクルにおける環境負荷を評価する手法
「ライフサイクルアセスメント(以下、LCA)」とは、製品やサービスのライフサイクルにおける環境負荷を定量的に評価する手法のことです。ライフサイクル全体またはどこか特定の段階において、「どれくらいの環境負荷があるか」を数字で明らかにしていきます。
当時も決してメジャーではなかったです。80年代後半くらいからLCAの研究を始めたかたもいますが、90年代は今以上に専門家のみにおける世界だったのではないでしょうか。
私はペットボトルの後は、普通の「プラスチックのリサイクル」についても研究しました。LCAを研究すると、環境負荷を評価するために様々な技術も調べなくてはいけません。 今回はその経験を活かし、お話ができればと思っています。
意外にもライフサイクルの把握が困難な「繊維製品」

衣服のライフサイクル*は、他のリサイクル製品と比べると情報が少ないのが大きな違いでしょう。
自動車を例に挙げてみると、自動車は何万点という多量の部品を使用していますが、どのメーカー・関連会社によって製造されているかは明確です。鉄やアルミといった素材の違いに限らずある程度の追跡ができるため、自動車にまつわる環境負荷を正確に評価することができます。 (*ライフサイクル…ここでは、製品の一生を表す)
では衣服はどうでしょう。衣服はそもそも、評価時のベースとなる「代表選手」を選ぶのが難しいのです。自動車はスペックが明確なこともあり、「何人乗りの排気量○○ccの自動車」のように代表的な製品を決めることが容易です。 しかし衣服は誰一人として同じものを着ていないため、「代表」がなにかを指定することが難しいです。
たしかにTシャツはメジャーな衣服ですが、LCAの評価において「代表的な服なのか」というとそうとも言い切れせん。Tシャツの素材は製品によって異なりますし、たとえ素材が分かったとしても、1つ1つの製造工程まで遡って評価することは難しいからです。「このメーカーのTシャツは△△産の糸が使われ、○○といった製造工程を経て消費者に届いている」ということはなかなか分からないのです。
自動車以外を例に挙げてみると、石油製品は石油の産地が大まかには明らかになっていますが(=代表的な場所は分かるが)、「木綿の糸」がどこ産なのかを表示しているケースはほとんどありません。縫製工場の国名しか書かれていないことが多く、それ以上はさかのぼれないのです。
①評価時の「代表」が決めづらく、②製造における情報が少ない・もしくは分散している、これが繊維製品(特に衣服)と他のリサイクル製品の違いと言えます。
「合成繊維」と「天然繊維」:環境に良いのはどっち?
1.ライフサイクルアセスメント(LCA)の評価で比較した場合
先ほどの「繊維製品(特に衣服)と他のリサイクル製品の違い」と絡めて考えてみると、合成繊維である「ポリエステル」は、原油からの精製・合成プロセスが明らかになっているため、環境負荷を把握することはほぼ可能といえます。
一方で綿などの「天然繊維」は、地域によって綿花栽培の仕方・羊の育て方・農家の規模が違います。 過剰に肥料や薬品を使っている…という話も稀に耳にしますが、これらは使われている場合も使われていない場合もあり、つまりは「同じ天然繊維」でも、栽培の方法・環境が異なるため環境負荷に差が生まれています。環境負荷の把握は容易ではなく、「合成繊維」・「天然繊維」の比較は難しいです。たとえ「天然繊維」でも、それが環境に悪い生産工程を経ていれば、LCAの評価は「合成繊維」より悪い場合もあり得ます。
2.温室効果ガス(CO2)の排出量で比較した場合
温室効果ガス(CO₂)排出量を中心としたデータの平均値でいえば、「ポリエステル(合成繊維)」よりも「綿(天然繊維)」の方が環境負荷は少し低いといわれています。しかしこれは、あくまでCO₂ を指標とした場合であり、重要なのは「環境負荷はCO₂だけでは無い」ということでしょう。
「オーガニックだから環境負荷が低い」は間違い?
実は有機栽培だからといって、「環境負荷が低い」とは限らないんです。「オーガニック」と聞くと環境に良いイメージを抱いてしまいがちですが、実際にオーガニックコットンの環境負荷がどのくらい低いのかは、あまり明確ではありません。オーガニックコットンをうたっていなくても環境に配慮している場合もあれば、オーガニックコットンをうたっていても、酷い環境下で生産されている場合もあります。
さらに「環境」という問題は、「物」だけではなく「人」をも取り巻くものです。
2013年にバングラデシュの縫製工場が入っていたビルが崩落した事故*がありましたが、事故前の段階でビルの安全性が損なわれていたことは分かっていたようで、環境の劣悪さが指摘されています。しかし世界にはきちんと整った環境で働いている人々もたくさんいますよね。繊維製品において、ライフサイクル上に存在するこのような「差異」が明確に分かることはありません。
* ダッカ近郊ビル崩落事故:2013年4月、バングラデシュの首都ダッカで、8階建ての商業ビル「ラナ・プラザ」が崩壊した事故。死者1,134人、負傷者2,500人以上の多くが、このビルに入っていた縫製工場で、低賃金かつ劣悪な環境のもと働いていた若い女性たちで、ファッション史上最悪の事故とも呼ばれています。(参照:CNN「バングラデシュのビル倒壊、死者増加は残骸処理の重機原因か」)
環境への影響を「CO2だけ」で評価してはいけない

現在の日本では、気候変動対策が政策として重視されているため「温室効果ガス(CO₂)の排出」を重視することが多いです。とはいえど、”温室効果ガス(CO₂)以外の要素も合わせて評価すること”に意味があるんです。たとえば「水」が使われている製品やサービスであれば、使用した水を排出した際の近隣の淡水域・海水域への影響についても、評価しなければいけません。
LCAという手法自体は、「解決方法を示すこと」が目的ではありません。求められるのは「環境負荷を低減する解決方法」ではなく、評価を見て「総合的に判断すること」です。
全ての項目を「金額」に換算し統合評価するという方法もありますが、あまり支持されていません。それよりも各項目をきちんと正しく評価し、理解していることが大事なのです。その次に、比較する基礎となる「分析データ」を持っていることが重要になります。 今の日本では、欧州のように「製品のサプライチェーンにおける上流の関連情報」を全て把握していることが徐々に求められつつあると思います。
| >>第2回へつづく ※「繊維リサイクル」関連のそのほか記事は、こちらからご覧ください。 |