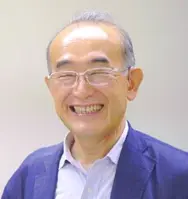2022.11.10
東大・平尾教授とひも解く繊維リサイクルの今~第2回・ペットボトルのリサイクルの真実を暴く~
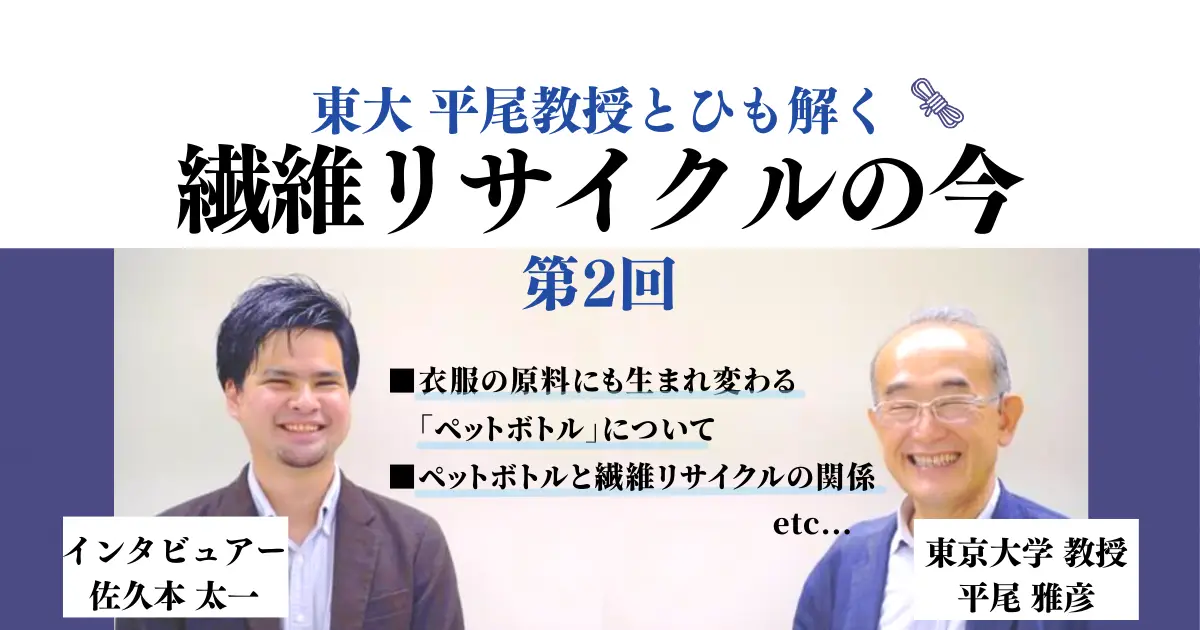
目次
前回の記事では平尾教授の専門である「ライフサイクルアセスメント(LCA)」という視点から、衣服の環境負荷を測定する難しさや、 環境負荷への正しい考え方を伺いました。
第2回は、国内で最もリサイクルが進んでいる製品「ペットボトル」についてお届けします。ペットボトルのリサイクル先はさまざまで、ふたたびペットボトルになるものもあれば、「繊維(ポリエステル糸)」に生まれ変わるものもあります。

| 平尾 雅彦:東京大学 先端科学技術研究センター 教授 工学博士 (写真右) |
| ライフサイクルアセスメントを通じて、消費と生産パターンの変革を目指した研究をおこなっている。製造・輸送・回収・リサイクルの技術から、生産者や消費者への情報提供、社会制度の設計などのフレームワークづくりも。 サイクリングと、愛犬(長野県天然記念物の川上犬)との散歩が趣味。学生時代には、キャンピング自転車で岐阜県大垣から島根県出雲までを走破。 |
| 佐久本 太一:日揮ホールディングス株式会社 サステナビリティ協創部 (写真左) |
| 沖縄県出身。学生時代は木質バイオマス分解菌の遺伝子分析や、次世代シーケンサーを用いた菌叢解析などを研究。2019年に日本エヌ・ユー・エス株式会社に入社後、日揮ホールディングス株式会社 サステナビリティ協創部に出向し、廃繊維・廃プラスチックの資源循環ビジネス開発を担当。ダイビングとプロレス観戦が趣味。故郷の沖縄でも資源循環を達成し、美しい自然を守るのが夢。一緒に達成する持続可能なパートナーも募集中。 |
ペットボトルとリサイクルの関係性
「リサイクル」を前提に考えられた製造ルールがある
ペットボトルには製造に関する基準があるものの、法的な規制ではなく、生産者の団体の合意によってつくられた規格です。具体的な基準の例は以下です。
|
これらのルールは日本で生産されるペットボトルすべてで守られているため、国内のペットボトルを集めると、全部が透明かつ素材が明確です。 そのため、「リサイクルを前提に考えられたペットボトルの製造ルールが存在している」といえるでしょう。
ペットボトルはなぜ分別が必要なのか?
理由は、「リサイクルをしやすくするため」です。ペットボトルをはじめとする”飲料物”をつくる素材には、「飲料用途由来の廃棄物からリサイクルしたものでなければいけない」というルールがあります。
そのため他のものと混ざらないよう、ペットボトルは分別回収されるのです。 ペンキなど飲料以外を入れたときは、分別して出さないでくださいと言われたりもします。
ペットボトルは潰して捨てるとダメって本当?
まず法律に関しては、「容器包装リサイクル法」の採択が「ペットボトルリサイクル」を浸透させた要因の1つだといえるでしょう。
それ以外には、「自治体」が一般家庭におけるゴミ分別の必要性を周知したことがキッカケです。また、自動販売機の横にペットボトルの回収ボックスが配置されているのをよく見ると思いますが、これは国ではなく業界の判断によって決められています。以前、とあるメーカーが「つぶしやすくなったペットボトル」にフォーカスしたTVCMを流したことがありましたよね。ペットボトルのリサイクルを認知に大きく貢献したと思います。
しかし、実はペットボトルをねじるのは良くないんです。リサイクル工場では、キッチンのミキサーと同じような仕組みで「回転する歯」でボトルを切っているので、上から圧をかけて縦につぶしたり、ギュッと横にねじりこむだけでボトルの強度が上がって、回転歯がボロボロになってしまいます。つまりリサイクルの妨げになってしまうんです。ペットボトルをリサイクルしやすくするためには横から力を掛け、ぺっちゃんこになるよう薄くつぶして捨ててくださいね。
衣服・ペットボトル・容器包装のリサイクルを比べる
容器包装と違い、自治体は「衣服」をどのように回収・リサイクルするかという方法論を持っていません。そのため現在は「リサイクルを担っている事業者のやり方」に従って衣服を集めることがほとんどです。具体的な指示例は、 「まだ着られそうなもの、かつ洗濯し終わった綺麗な衣類だけを出してください」といったものです。
日本において、ペットボトルや容器包装のリサイクル方法はしっかりと統一されています。容器包装リサイクル協会*は国の機関ではなく”業界団体”であるものの、国と調和を取りながらリサイクル基準を設けています。リサイクルにまつわる一連のスキームも、同様に容器包装リサイクル協会が監査をしているので「適当に容器包装を集めてきて燃やした」などはもちろん認められていません。 これが、衣服にまつわるリサイクル(繊維リサイクル)と、ペットボトル・容器包装リサイクルの違いといえるでしょう。
*容器包装リサイクル協会: 「容器包装リサイクル法」に基づく指定法人として、特定事業者等からの受託に基づき、市町村から委託される分別基準適合物の再商品化を行い、あわせて、再商品化事業に関する普及・啓発および情報の収集・提供等を行っている団体。
【比較①】容器包装プラスチックとペットボトルの環境負荷
容器包装プラスチックの製造工程は、まずプラスチック原料からフィルムや成形ボトルを作った後に印刷・内容物を充填し、製品として販売しています。この工程は複雑ではないため、環境負荷はそこまで高くありません。
次に合成繊維の環境負荷は、「ポリエステル1kgでできている繊維」が「1kg分のポリエステルの環境負荷だけか」というと、それだけではないのがポイントとなります。原料ポリエステルを繊維に加工する工程や染める工程、布に紡績する工程など、全ての工程を「合成繊維の環境負荷」として考慮する必要があるからです。
ちなみに染める工程では、大量の水、化学物質を使用します。 「裁断くず」もたくさん出るため、容器包装に比べ、合成繊維の「製品になるまでの環境負荷」は極端に高くなってしまうんです。
【比較②】衣服とペットボトルのリサイクルのしやすさ
飲み終わったペットボトルをリサイクルしようとすると、色が付いていない純粋なPET=ポリエステル樹脂が選別されるため、シンプルな工程でリサイクルが可能です。 キャップの素材はPETではありませんが、水に放り投げてみると、比重の違いから簡単に分別できるよう工夫されているんです。しかし衣類は違い、服を水に放り込んだとしても素材ごとに分かれてくれません。
色つきの繊維や、2種類以上の原料が混ざっている混紡では、素材を分けることが難しくなります。複数の素材が一緒に縒(よ)られて糸になっていたり、表地はウール・裏地は異素材など、衣類のリサイクルは複雑なのです。さらに細かく見ると、縫い糸は合成繊維なのか、天然繊維なのかぱっと見では分かりません。
そのため、衣服のリサイクルにおいては「分けにくいこと」が課題です。リサイクルを前提としたものづくりをするとき、素材はなるべく単一であるほうが良く、さらには製品を作る時だけの環境負荷ではなく、「リサイクルするときの環境負荷」も考えることが重要です。
ペットボトルを何にリサイクルすべきか、決めるのは難しい

多くのペットボトルは「糸(繊維)」にリサイクルされている
現在、ペットボトルのリサイクル先の多くは「糸(繊維)」が占めています*。ペットボトル由来の繊維を使用していることを示す「PETボトルリサイクル推進協議会のリサイクル推奨マークタグ」がついている製品もあります。
 (参考:ANKEN「 PETボトルリサイクルシステム」のイラストを元に作成)ペットボトルから「糸(繊維)」にする方法は、ペットボトルを粉砕・洗浄→繊維の形(糸)に成形→製品へと加工 という順番です。 *注釈受け:ペットボトルのリサイクル先の割合について そして糸(繊維)を製造する場合、石油から新しく作る「新しい糸」より、「ペットボトルをリサイクルした糸」の方が環境負荷が低いことも明らかになっています。しかし、これがペットボトルにとって良いかは別です。 なぜかというと、ペットボトルをペットボトルにする技術(ボトルtoボトル)と、ペットボトルを糸にする技術(ボトルto繊維)は、どちらも近しいものです。そのため、ペットボトルを「糸(繊維)」に生まれ変わらせるべきなのか、それとも再度「ペットボトル」に生まれ変わらせるべきなのか、答えを出すのは難しいんです。
(参考:ANKEN「 PETボトルリサイクルシステム」のイラストを元に作成)ペットボトルから「糸(繊維)」にする方法は、ペットボトルを粉砕・洗浄→繊維の形(糸)に成形→製品へと加工 という順番です。 *注釈受け:ペットボトルのリサイクル先の割合について そして糸(繊維)を製造する場合、石油から新しく作る「新しい糸」より、「ペットボトルをリサイクルした糸」の方が環境負荷が低いことも明らかになっています。しかし、これがペットボトルにとって良いかは別です。 なぜかというと、ペットボトルをペットボトルにする技術(ボトルtoボトル)と、ペットボトルを糸にする技術(ボトルto繊維)は、どちらも近しいものです。そのため、ペットボトルを「糸(繊維)」に生まれ変わらせるべきなのか、それとも再度「ペットボトル」に生まれ変わらせるべきなのか、答えを出すのは難しいんです。
重要なのは「リサイクルしたあと」の選択肢
まず、②の「ペットボトル→糸」から考えてみましょう。
ペットボトルを糸(繊維)にリサイクルする工程では、環境負荷は実はあまりかかりません。しかし重要な点は、「ペットボトルから製品(衣類)になったその後」です。現状で「繊維(糸)を元の繊維に戻す技術(「繊維to繊維」)」は、社会に広く実装されていません。ということは「ペットボトル→糸」にリサイクルされたあとは、それ以上リサイクルすることができず、「廃棄」を選択するしかありません。
続いて、①の「ペットボトル→ペットボトル」の場合は②「ペットボトル→糸(繊維)」と比べ、製造工程での環境負荷は少し高くなります。ですが今は、ペットボトルからペットボトルに生まれ変わった後も、またボトルへリサイクルすることができ、「ペットボトル→ペットボトル→ペットボトル・・・」と複数回、循環して利用が可能です。 (※無限ではありません。)
ここで、1kgの繊維を作ると仮定してみましょう。
環境負荷は、石油から新しい繊維を作るより、「廃棄されたペットボトル」から作った方が低いです。しかしリサイクルで作られた製品を使い古したあとは、先ほども話した通り「廃棄」せざるを得ませんよね。せっかくペットボトルを「繊維製品」へと生まれ変わらせたのであれど、その後は「廃棄」しか選べないのであれば、「本当に環境にやさしいか」には疑問が生まれます。これらのことから、再生時に少しエネルギーがかかっても、その後も繰り返し利用できる「ペットボトル」に再生した方が良いかもしれないと考えることができます。
| >>第3回へつづく ※「繊維リサイクル」関連のそのほか記事は、こちらからご覧ください。 |