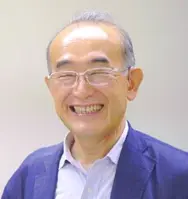2022.11.22
東大・平尾教授とひも解く繊維リサイクルの今~第3回・法律とリサイクルと消費者と~
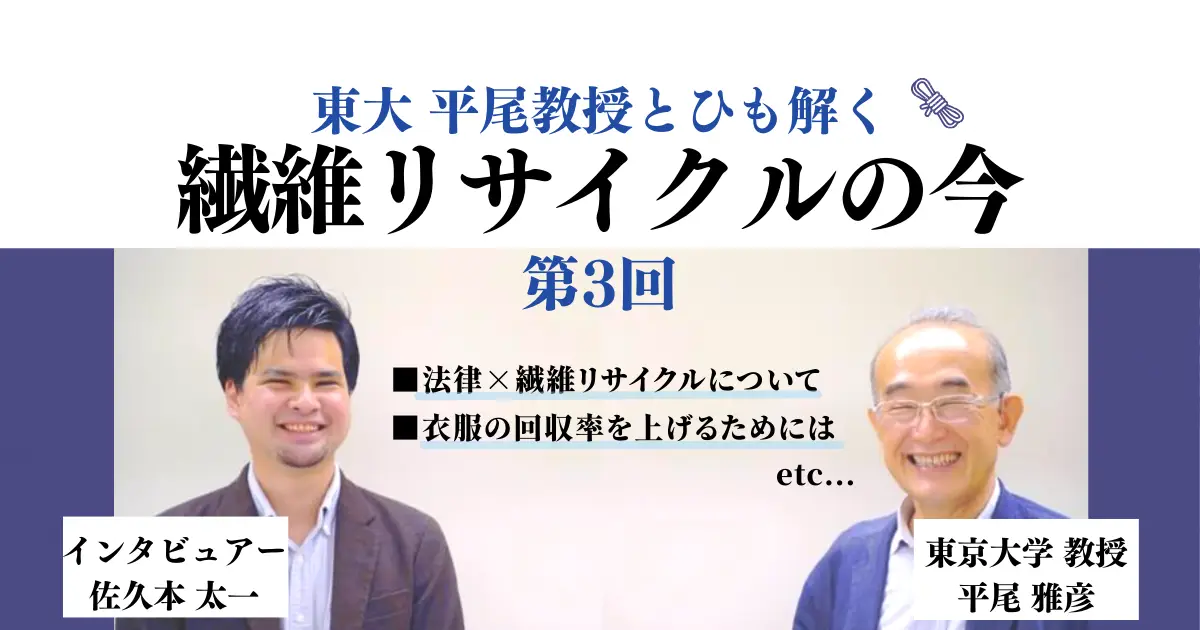
目次
前回ご紹介したように、私たちにとって身近なペットボトルや容器包装(肉や魚のトレー・卵パックなど)のリサイクルは、「容器包装リサイクル協会が設けた基準」をもとにおこなわれています。ところが、「衣服」のリサイクルに関する法律は2022年8月時点では存在しません。
法律が採択されるまでには多くの時間を要するため、地球環境を守るためには「衣服の回収・衣服のリサイクル技術開発」を進めていく必要があるでしょう。そこで今回は、「衣服の回収・衣服のリサイクル技術開発」のために必要なアクションを解説していただきました。
>>第1回・第2回はこちらから |

| 平尾 雅彦:東京大学 先端科学技術研究センター 教授 工学博士 (写真右) |
| ライフサイクルアセスメントを通じて、消費と生産パターンの変革を目指した研究をおこなっている。製造・輸送・回収・リサイクルの技術から、生産者や消費者への情報提供、社会制度の設計などのフレームワークづくりも。 サイクリングと、愛犬(長野県天然記念物の川上犬)との散歩が趣味。学生時代には、キャンピング自転車で岐阜県大垣から島根県出雲までを走破。 |
| 佐久本 太一:日揮ホールディングス株式会社 サステナビリティ協創部 (写真左) |
| 沖縄県出身。学生時代は木質バイオマス分解菌の遺伝子分析や、次世代シーケンサーを用いた菌叢解析などを研究。2019年に日本エヌ・ユー・エス株式会社に入社後、日揮ホールディングス株式会社 サステナビリティ協創部に出向し、廃繊維・廃プラスチックの資源循環ビジネス開発を担当。ダイビングとプロレス観戦が趣味。故郷の沖縄でも資源循環を達成し、美しい自然を守るのが夢。一緒に達成する持続可能なパートナーも募集中。 |
リサイクル費用の仕組み

現在のリサイクルの仕組みの上では、「リサイクル製品を売る側」と「購入する側」で「コストにまつわるギャップ」が生まれてしまっています。理解するために、まず同商品の「新しく作られた製品」と「リサイクルされた製品」の価格・品質を比べてみましょう。
| 価格:新しく作られた製品 < リサイクルされた製品品質:新しく作られた製品 > リサイクルされた製品 |
このように、リサイクルされた製品は新品と比較して価格が高く、品質も劣りがちというわけです。リサイクル品を購入する側としては、品質が劣るのであればせめて”安く”買いたいですよね。しかし売る側はどうでしょうか。「リサイクル」には一定のコストがかかっていますから、「安く売ることは難しい。」という考えを持っています。これが、購入者と売る側の間で生じている「ギャップ」です。
はい。しかし、家電も自動車も「リサイクル費用」の負担の仕組みはそれぞれ異なります。家電は、クーラーを1台を捨てるだけでも「リサイクル費用」を払う必要がありますよね。
そして自動車は、新しく購入する際に必ず「リサイクル費用」を払っているんです。 新車には「リサイクル券」がついてくるのですが、中古としてその車を売るときには「リサイクル券」も一緒に売却する制度になっています。売りに出さずそのまま廃棄するときには、その券によってリサイクル費用を賄うことになります。自動車は「購入者」が、家電は「排出者(捨てる人)」が、「リサイクル費用」を負担する仕組みになっているんです。
焼却処理とリサイクル、環境に良いのはどっち?
焼却処理側とリサイクル側で意見が揃いにくい理由
焼却処理においては、石油由来である「プラスチック」が多く含まれていれば含まれているほどよく燃える特徴があります。そのため焼却処理で生じる熱をエネルギーとして再利用するサーマルリカバリーの関係者は、「ゴミがたくさん集まれば多くのエネルギーに転換できる!」といった意見を持っています。しかし、リサイクル事業者の視点から見れば「ゴミが多いこと」にメリットは感じられないですし、それぞれの思考・価値観が反対の方向に向かっているわけです*。
このような事象は「ゴミ分別」の観点でも起こっており、焼却工場側は「分別しなくてもいい(=ゴミが多いと転換できるエネルギー量が多くなるため)」と言っている一方、リサイクル事業者は「しっかり分別してほしい」と言っています。
実は日本では、環境省が大型焼却炉とリサイクル処理のどちらにも補助金を出しているんです。つまり、環境省が「リサイクル」と「廃棄物処理」という両面も担当しているため、このような状況が生まれているといえるでしょう。
*編集部注:サーマルリサイクルは、日本ではシェアが大きいリサイクル方法とされていますが、欧州などではその環境負荷からリサイクル方法とみなされていません。
今までも環境負荷を評価する際、「製品はどのように処理、もしくはリサイクルされると環境負荷が低いのか」について様々な議論をおこなってきました。しかし、この解答は必ずしも簡単に示せるわけではありません。重要なのは「評価を見て総合的に判断すること」なので、これからもその視点を忘れずにおこなっていきたいです。
繊維リサイクルに重要な「消費者」の存在

捨てられた服の行方が分かりにくいのはなぜか
「不透明」に見えてしまう原因は、「リサイクル事業者」と「実際に衣服を回収する業者」では「欲しいと思う衣服の定義」が異なるからではないでしょうか。
リサイクル事業者の視点から見ると、リサイクルできるポリエステル素材であれば、着古した服・下着だとしても「リサイクルに出して欲しい」と思います。しかし、実際に衣服を集める業者の視点に立つと、需要があるのは「リサイクル」ではなく「リユース」です。そのため、ひどく着古したものや下着は古着として機能せず、回収できないというケースが大半です。このような点から、衣服が廃棄後、または回収後に、どのような処理をされているかが不透明に見えるのでではないかと推測しています。
いろいろな産業や業界の方々が疑問や課題を出し合った上で、「サプライチェーン全体の環境負荷が下がるメソッドの提案」をすることが重要でしょう。このような場面においては、我々のような学者も共に試行錯誤ができると考えます。
さらに「繊維リサイクル」においては、消費者も一緒に行動をしないと「循環型社会の実現」が難しいと感じています。前回でもお話した「ペットボトル」は、一般社会においても「リサイクルをする」という意識が根強いですよね。そのためか、ペットボトルは全体の約9割が回収されているのに対し、繊維の回収割合は4割程度にとどまっています。繊維製品の回収率を上げるためには、消費者の行動と認知を広めることが非常に重要だといえるでしょう。
| >>第4回へつづく ※「繊維リサイクル」関連のそのほか記事は、こちらからご覧ください。 |