前編【プラント建設の未来を支える技術者たち #06】HSEのエキスパート
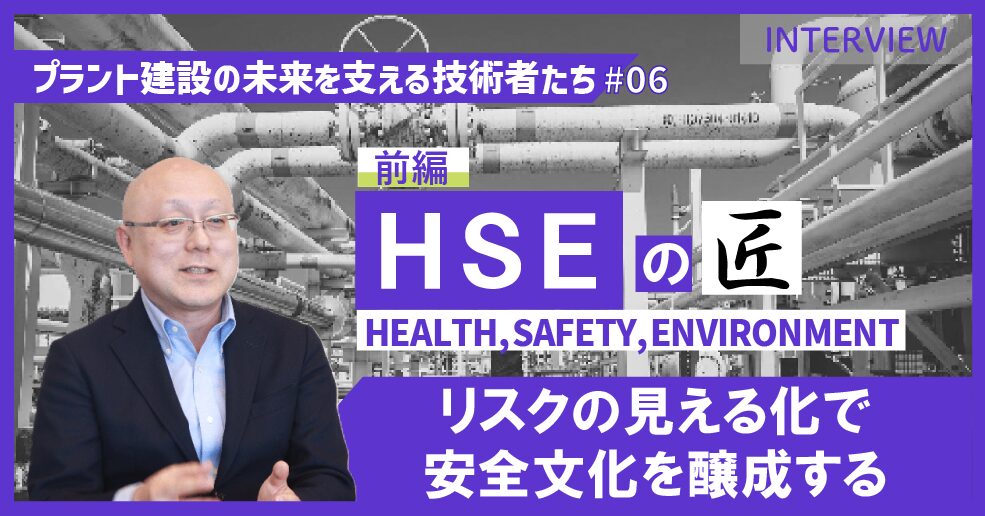
目次
海外のプラントの設計・調達・建設を事業の柱とする日揮グローバルでは、幅広い分野の技術エキスパート*が事業の根幹を支えています。彼らの持つさまざまな専門技術はプラント建設だけでなく、サステナブルな社会を実現するうえでも欠かせないものです。そこでサステナビリティハブでは、チーフエンジニア**の方々に専門技術や最新トピックなどを解説してもらうインタビュー記事を連載しています。
第6弾となる今回のテーマは、「HSE」。HSEの黎明期から成熟までを第一線で支えてきた田邊エンジニアに、HSEの概要や人材育成の取り組み、HSE分野における最新トピックスまで、じっくりと語っていただきました。(インタビュアー:サステナビリティハブ編集部)
* エキスパート制度は、日揮ホールディングス、日揮コーポレートソリューションズ、日揮グローバル、日揮が対象
** チーフエンジニアは、チーフエキスパートとリーディングエキスパートの総称

HSEとは?
――本日は、HSEの専門家として長年ご活躍されている、チーフエンジニアの田邊さんにお話を伺います。まず、HSEとはどういったものなのか教えていただけますか?

HSEとは、Health, Safety, Environmentの頭文字をとったもので、労働安全衛生、プロセス災害や、環境事故などが起こらないようにするためのフレームワークのことをいいます。
危険な化学物質を扱う化学プラントは、漏洩事故などのリスクと隣り合わせです。このような「プラント内で取り扱っている危険物質を起因とする事故」を「プロセス事故」と呼びます。
日揮グローバルがおこなっている「テクニカルHSE」は、技術的な側面から「プロセス事故」を未然に防ごうという取り組みです。(日揮グローバルでは、HSEとテクニカルHSEを以下のように区分しています)
- HSE: 職場や工事現場での労働災害防止の安全管理が中心
- テクニカルHSE:プラント設計における漏洩事故災害防止のための安全管理が中心
――具体的にはどういったことをするのでしょうか。
万が一事故が起きても被害が広がりにくいように、敷地配置計画を立てたり、緊急時の対応設備や手順などを設計に落とし込んでいったりします。加えて、事故の原因となる故障やエラーを特定して防止策を立てることも重要な取り組みになります。
――プラント操業時に起こり得るリスクを想定して、設計段階から事前に安全対策をしているわけですね。幅広い知識や技術が必要とされそうですね。
実際には、HSE担当者だけでできることではないので、様々な専門部の方々と相談しながら合理的に反映できる範囲で安全な設計を達成していくというイメージです。
そうした意味で、HSEを達成するための技術としては、本質安全と呼ばれる「このように安全設計をした方がいいよ」というようなGood Practiceの知識や、安全性を評価する解析技術、さらにはエンジニアリング業務遂行中に実際に設計要素を適切に安全な方向に持って行ってもらうためのコミュニケーションスキル、などが必要な要素だと思います。
プロセス安全マネジメントとテクニカルHSEの関係は?
――安全衛生の分野では「プロセス安全マネジメント」という言葉もよく耳にしますが、テクニカルHSEとの関連性について教えていただけますか。

テクニカルHSEは、アメリカをはじめ海外では「プロセス安全(プロセスセーフティ)」とも呼ばれている分野になります。
「プロセス安全マネジメント」というのは、もともとはアメリカの労働安全衛生局(OSHA:Occupational Safety and Health Administration)が導入した言葉で、操業プラントの設備安全性を組織内で適切に管理する仕組みを指し、PSM(Process Safety Management)とも呼ばれるものです。我々がおこなっているテクニカルHSEも、基本的にはこの「プロセス安全マネジメント」のジャンルに入ります。
HSEやプロセス安全という概念は、設備設計をおこなう組織のメンバーや操業プラントを運転する組織のメンバー全員が意識を高めなければ達成できません。ですから、「組織内でプロセス安全が関連する操業要素を特定し、安全性を高めるための組織・制度を仕組みとして導入する」という考え方がベースになっています。
――テクニカルHSEは「プロセス安全マネジメント」の系譜にあるということですね。
はい。ですが近年設備設計フェーズでは、「セーフティケース」と呼ばれる概念も導入されてきており、より高度なテクニカルHSE対応が求められるようになってきています。
HSEには2つの大きなフレームワークがあり、1つは今お話しした、アメリカ発祥の「プロセスセーフティマネジメント」のアプローチで、もう1つが、イギリス・EU発祥の「セーフティケース」のアプローチになります。
「セーフティケース」は、「事故になりそうなシナリオを想定し、そのポイントをしっかりおさえて、リスクが具現化しないような設備設計にしたうえで、残っているリスクについても、留意点や対応策について事前に周知する」というものです。つまり、「設備設計から操業まで一気通貫で安全性を守っていきましょう」という考え方ですね。今は、この「セーフティケース」が業界の主流で、スタンダードとして定着しつつあります。
HSEの導入と普及の歴史
――HSEが活発に導入されているのは、主にどういった業界でしょうか?
主に石油・ガス業界など、化学物質を扱うプラントですね。加えて、イギリスやEUの一部の国では原子力関連の業界にもHSEが導入されています。
――HSEの考え方は、いつ頃からプラント業界に持ち込まれ、どのように普及してきたのでしょうか。

私が入社した1998年は、いわばHSEの黎明期で、まだ業界でも社内でも今のようにHSEのスタンダードが確立されておらず、「HAZOP(Hazard and Operability Studies)」という手法がようやくプロジェクトに導入され始めた頃でした。その後、プロジェクト内でHSEに関する課題を解決するために知識を蓄積していく中で、徐々にフレームワークが確立されていき、包括的なアプローチで安全性を高める現在の手法がスタンダード化したという印象です。
約30年前は、1プロジェクトにHSE担当が1人いればいい方という感じでしたが、今では1プロジェクトに4,5人のHSE担当者がつくほど、対応すべき内容も増えましたし、業界全体に浸透しています。
――HSEを導入するようになってからの約30年で、プラントの安全性は高まったと感じていますか。
テクニカルHSEやプロセスセーフティが育ってきた背景には、過去の大事故があります。事故が起こるたびに安全対策の強化がなされ、今に至っているわけです。そうした意味では、過去に比べて確実に安全性は高まっていると感じますし、実際に海外の専門家は事故率も下がっていると言及しています。
一方で、「これ以上する必要はないのでは?」というくらいまで、HSEの対応が進んでいく中で、事故率の下げ止まりが起きていることも指摘されています。
そこで近年注目されているのが、人材教育です。「プロセス安全やHSEといった分野を良く知っている優秀な若者をどんどん増やしていくことで、安全性を底上げしていこうという」という流れが国内外で生まれています。例えば、海外の学術学会でも、「教育プログラム」がひとつの独立したセッションとしておこなわれていて、注目度の高さを感じます。
人材育成の取り組みについて
――田邊さんは長年、社内外で人材育成のための活動をされてきたそうですね。詳しくお伺いできますか。
社内教育に加えて、産業界と学術界をつなぐ橋渡しとして横浜国立大学での教育・研究活動や安全工学会での委員活動をおこなってきました。特に、2013年から受け持っている横浜国立大学での講義は、ライフワークとして力を入れて取り組んできました。
――人材育成が世界的な潮流になるだいぶ前から教育活動に力を入れてきたのには、どんな理由があったのでしょうか。
1970年代くらいまでは海外も日本も安全性に関しては同じ技術レベルでしたが、1980年代に海外で「リスクベースアプローチ」と呼ばれる「リスクを把握し、それに対してどのように設備設計、管理をしていくか」という合理的な考え方が導入されてから、安全性の面での技術格差が出てきてしまい、このことに危機感を覚えていました。
海外では「リスクベースアプローチ」がスタンダード化している一方で、日本はいまだに浸透していません。さらに海外ではシステマチックな教育プログラムで優秀な若い世代も育ち初めています。日本はまだそのあたりが追い付いていない部分があるので、これまでのプロジェクト経験で自分が得た知見をもとに、教育を通して全体を底上げすることに貢献出来たらという思いでやっています。
――リスクベースアプローチが日本に根付かなかったのには、何か理由があったのでしょうか。

日本では「リスク」を「危険性が残っている」とマイナスに捉える風潮にあるため、あまり積極的には導入されてこなかった、と一般的には言われています。
ですが、私が実際にプロジェクトで海外の方・日本の方と接してきた肌感覚では、そこまで「リスク」に対しての感じ方に差はないように思います。もし差があるとすれば、日本では小学校から高校まで「リスクとはどういうものなのか?」という教育を受ける機会がないため、「リスク」について考える機会がなかったことなのではないかと考えています。日本人は学習能力が高いですから、「リスクとは何なのか?」ということを学んで理解すれば、リスクベースアプローチの考え方も浸透していくはずです。
――そうした思いも、今の教育活動につながっているわけですね。
草の根活動のようなものですが、継続するうちに少しずつ変わってくるのではないかという期待もあります。そもそも、「リスク」というのはプラントの安全という特定の分野だけでなく、生きていく上でも役に立つものです。今は、色々なことを考慮して自ら決断していかなければいけない時代です。「どこに危険があるか?」を自分でしっかりと認識した上で決断するリスクベースのアプローチは、時代に合った考え方だと思っています。
HSE分野における最新トレンド
――HSE分野における最新トピックがあれば教えてください。
HSEやプロセス安全の分野でも、「デジタル化」や「AI」といったトピックが多くみられるようになってきました。国内では、デジタル技術を用いて安全性を向上させていく「スマート保安」の取り組みが広がってきています。このような流れの中で、近年はマネジメントにおいて、デジタル技術とリスクベースアプローチを組み合わせ、合理的な判断ができるようになることが求められています。
この潮流の中で、当社もスマート保安技術の一つとして「CoreSafety」というSaaSビジネスを立ち上げました。
――プラント建設で培ってきたHSEの知見をいかして、サービスを立ち上げたわけですね。詳しくお伺いできますか。
CoreSafetyは「リスクを可視化することで、操業リスクマネジメントを合理化する」というコンセプトでつくった、プラント向けのリスク管理アプリのサービスです。イギリスの原子力業界で使用実績がある事故想定シナリオ管理台帳をベースに、リスク分析について高度な知識を持たない方でも直観的に操作できることを目指して開発しました。画面上で設備の保全・管理状況を入力していくことで、リスク情報が更新されるので、最新の管理状況を組織内で共有することができます。
この4月には、「漏洩」や「火災」といったプロセス災害だけではなく「転んでひざを怪我した」というような労働災害や、「有害ガスが発生した」というような環境事故のリスク評価もできる「OHS Module」も発売を開始しました。現在トライアル中のお客様の反響も良く、当面はこちらを主力として紹介していく予定です。
まとめ
今回の記事では、日揮グローバルの「HSE」のチーフエキスパートに、専門技術や最新トピックスなどについて伺いました。インタビュー後編では、HSEのチーフエキスパートとして活躍するに至った経緯や、仕事のやりがい、休みの日の過ごし方などをお伺いします。是非ご覧ください。
日揮グループのチーフエンジニアの詳細は、こちらをご覧ください。





